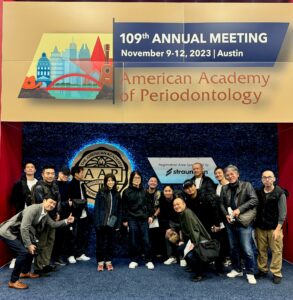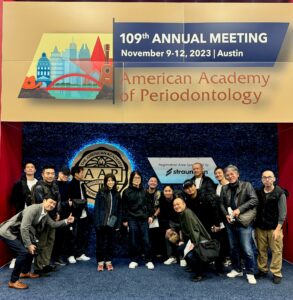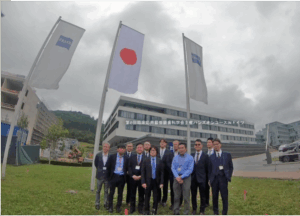医療は日々進化しており、今日「良い」とされている治療が、後に「害がある」と判明することも珍しくありません。臨床応用顕微鏡歯科学会では、顕微鏡治療にこだわるだけでなく、常に世界の最先端の医療情報を把握する事が重要だと考えています。秋山先生の方針に基づき、学会のメンバーは毎年、世界の著名な学会に直接参加し、世界の最先端の研究結果やリサーチ情報を入手しています。
アメリカ歯周病学会(AAP)
具体例を挙げると、2023年と2024年のアメリカ歯周病学会(AAP)があります。この学会は、世界の最高峰の歯周病学会であり、特にインプラントに関する発表が多いのが特徴です。
2023年のアメリカ歯周病学会(AAPオースチン開催)では、最大のカンファレンステーマが「津波(TUNAMI)」でした。この「津波」とは、インプラント周囲炎の急増を指しており、インプラント治療の深刻な課題として取り上げられました。さらに、2024年の110回アメリカ歯周病記念大会(AAPサンディエゴ開催)では、同じテーマの続編として「ナイトメア(Nightmare)」という演題で、再びインプラント周囲炎に関する集中討議が行われました。
これらの学会で示されたのは、インプラント治療に伴うリスクが、日本の歯科医師が考えているよりも遥かに高いと言う事実です。アメリカでは、インプラントが将来的に問題を引き起こす可能性があることがすでに常識となっており「インプラントの方が天然歯より優れている」という考えは、アメリカの学会ではほとんど見られなくなっており、やはり天然歯を守る事が重要である事が認識されています。
「インプラント周囲炎は手術の技術により防げる」という考えをよく言われますが、実際にはそうではありません。最新の研究では、インプラント周囲炎は「確実に起こりうる問題」であることが常識となっており、その発生率も論文により明確に示されています。
さらに、インプラント周囲炎は治療後経時的にその確率が経時的に増加する傾向にあります。「手術が上手だから」「インプラント経験豊富だから」と言って問題が起こらないわけではありません。どれだけ技術がたかくてもリスクをゼロにはできないのです。
現在、多くのインプラントはセメントで固定ではなく、スクリュ ーで固定する方式が主流です。以前は「セメントが歯肉内部に残ることでインプラント周囲炎が起こる」と考えられていましたが、細菌の研究では「スクリュー方式でもインプラント体と補綴物との境界部分のマイクロリーケージがインプラント周囲炎の大きな原因になる」と2024年AAPで発表がされています。